胃がんの特徴と末期症状|突然の別れに備える整理のポイント
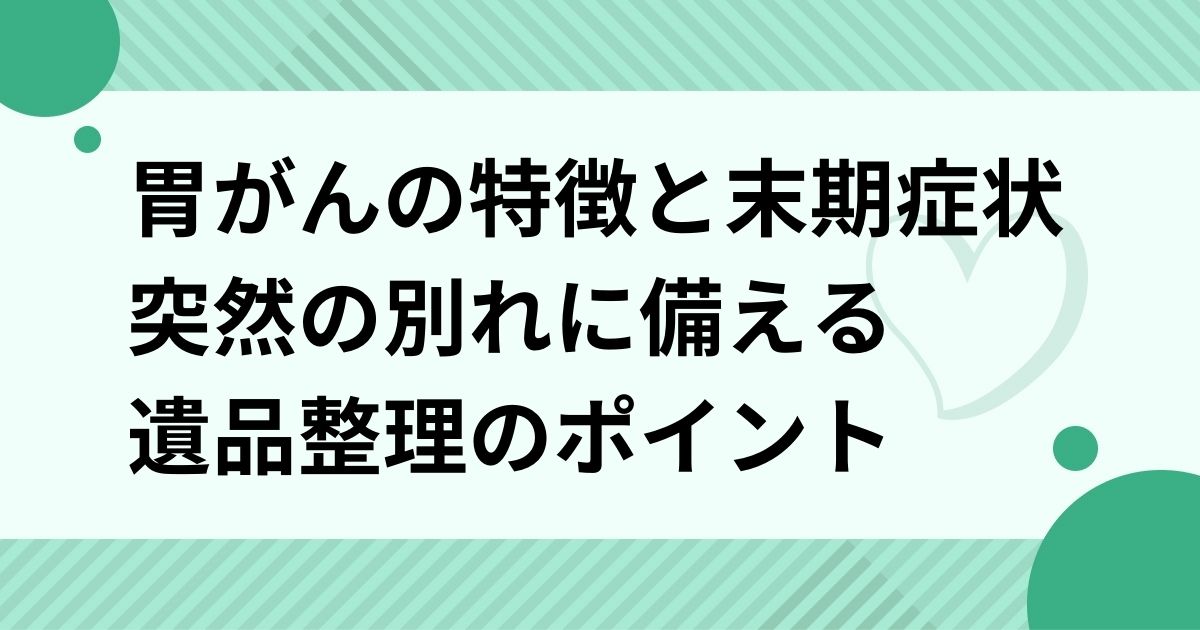
胃がんは日本で多くの人がかかるがんの一つです。自覚症状が少なく、進行するまで気づかないこともあります。そのため、診断されたときにはすでに病気が進んでいるケースも少なくありません。
特に末期になると、食事が取れなくなったり、体がどんどん衰えたりしていきます。家族にとってもつらい時間が続きますし、病状が急に悪化することもあります。もしもの時に備えておくことで、少しでも心の準備ができるかもしれません。
この先では、胃がんの特徴や末期症状についてわかりやすく解説しながら、家族ができる準備や遺品整理のポイントをお伝えします。
胃がんの末期症状と家族が知っておきたいこと
胃がんが進行すると、体にさまざまな変化が現れます。末期になると、以下のような症状が見られることが多くなります。
食欲不振と体重減少
胃の機能が低下し、食事が思うように取れなくなります。結果として、急激に体重が減ることがあります。
吐き気や嘔吐
消化がうまくできず、食べたものを吐いてしまうことがあります。
貧血や息切れ
胃の出血が原因で貧血になることがあり、顔色が悪くなったり、息切れを感じたりすることが増えます。
お腹の張りや腹水の蓄積
腹水が溜まると、お腹が膨らんで動くのがつらくなります。
こうした症状が進むと、患者さんは食事を取ることが難しくなり、少しずつ体力が落ちていきます。家族としては、どのように接したらいいのか、不安に感じることも多いでしょう。
無理に食べさせようとするのではなく、本人が少しでも楽に過ごせるように、医師や看護師と相談しながらサポートすることが大切です。
胃がんの種類と特徴
胃がんとは、胃の粘膜から発生する悪性腫瘍の総称です。大きくは「組織型(どの細胞から発生したか)」と「形態型(がんの広がり方や見た目)」の2つの観点から分類され、それぞれの特徴によって、進行速度や治療方法、予後が大きく異なります。
胃がんの90%以上を占める腺がん
胃がんの中で最も多いのが「腺がん」で、全体の約90〜95%を占めます。腺がんは胃の粘膜を覆う上皮細胞に由来し、さらに以下のように2つのタイプに分けられます。
分化型腺がん(分化型胃がん)
分化型は、がん細胞が腺構造(チューブ状の構造)を保ちながら増殖するタイプです。比較的ゆっくりと進行する傾向があり、早期に発見されれば治癒が見込めるケースも多くあります。
このタイプは、がん細胞が比較的「正常な細胞に近い形態」を保っているため、内視鏡検査などで発見されやすいという特徴があります。中高年の男性に多く、胃の中でも比較的上部(噴門部)や中部にできやすい傾向があります。
未分化型腺がん(未分化型胃がん)
一方で未分化型は、がん細胞がばらばらに散らばるように増殖するタイプで、腺構造を形成せず、細胞が密に詰まっていることが特徴です。進行が早く、発見時にはすでに胃壁の深くまで浸潤していることが多く、治療が難しくなる傾向があります。
未分化型は、若年層や女性にやや多く、胃の下部(幽門部)や全体に広がることがあり、症状が出にくいことから「沈黙のがん」とも言われています。
この未分化型に分類されるのが、特に注意が必要な「スキルス胃がん」です。
スキルス胃がん(びまん型胃がん)
スキルス胃がんは、胃の粘膜下層から筋層、漿膜といった深部に向かってびまん性に(広範囲にわたって)浸潤するタイプのがんで、胃の壁全体が硬くなり、厚みを帯びるようになります。
内視鏡では表面的な変化が目立たないため、発見が遅れることが多く、進行速度も速いため、発見されたときにはすでに腹膜やリンパ節、肝臓などへの転移が見られることが少なくありません。
スキルス胃がんは、特に若い女性に発症する傾向があるとされており、早期発見が難しいという点で、医学的にも非常に注意が必要なタイプとされています。
その他の胃がんの組織型
腺がん以外の胃がんは希少ではありますが、いくつかのタイプが存在します。
印環細胞がん(Signet Ring Cell Carcinoma)
未分化型腺がんの一種で、細胞内に粘液を多く含み、細胞の中心に核が押しやられて「印鑑の輪(signet ring)」のように見えるため、この名前が付いています。
このがんもスキルス胃がんと同様に、浸潤が早く進行しやすい特徴があり、転移しやすい傾向があります。特に女性や若年層で見られることがあり、注意が必要です。
粘液がん(Mucinous Adenocarcinoma)
がん細胞の間に大量の粘液が存在するのが特徴で、これも未分化型に分類されます。粘液によってがんが周囲組織に広がりやすく、治療が難しいこともあります。
扁平上皮がん・腺扁平上皮がん・カルチノイド腫瘍など
これらは比較的稀で、特殊な組織型に分類されます。扁平上皮がんは、通常は食道や皮膚などに多いがんですが、まれに胃に発生することがあります。腺扁平上皮がんは腺がんと扁平上皮がんの性質を併せ持つ混合型のがんです。
カルチノイド腫瘍は神経内分泌細胞由来で、進行は比較的遅いものの、胃酸の分泌やホルモンバランスに影響を及ぼすことがあります。
胃がんの種類を知ることの重要性
胃がんの種類を正確に知ることで、医師とともに最適な治療方針を選ぶための重要な材料になります。特に未分化型やスキルス型の場合は進行が速いため、家族としても「いつ、何を準備すべきか」を考えるうえで、病状の理解が極めて重要です。
家族が直面する負担と早めに考えたいこと
胃がんが進行すると、家族はさまざまな負担を抱えることになります。特に末期の段階では、患者さんを支えながら日常生活を送ることになり、心身ともに大きな負担がかかります。

主な負担として、以下のようなものが挙げられます。
- 精神的な負担
愛する人の病状が悪化していくことを受け止めるのはとてもつらいことです。先の見えない不安やストレスを感じることもあります。 - 身体的な負担
看病や介護が必要になると、夜間の付き添いや体位の変換などで睡眠不足になることがあります。また、体力的にも疲れがたまりやすくなります。 - 経済的な負担
治療費や入院費だけでなく、通院の交通費や介護用品の購入費などもかかります。仕事をセーブする必要が出てくると、収入面での不安が大きくなることもあります。
こうした負担を少しでも軽減するためには、周囲の協力を得ながら無理なくサポートできる体制を整えることが大切です。医療チームやケアマネジャーに相談し、介護サービスや支援制度を活用するのも一つの方法です。また、先のことを考えながら、必要な準備をしておくことで、少しでも心の余裕を持つことができます。
胃がんの終末期に備えてできること
胃がんが末期になると、家族は患者さんの生活を支えるだけでなく、もしもの時に備えてさまざまな準備を進める必要があります。急な状況の変化にも落ち着いて対応できるように、事前に考えておきたいポイントをまとめました。
1. 医療や介護の方針を決めておく
- 延命治療を希望するかどうかを、本人が話せるうちに確認しておく。
- 在宅療養か、ホスピス・緩和ケア病棟への入院を希望するかを検討する。
- 医師やケアマネジャーと相談し、利用できる医療・介護サービスを把握する。
2. 必要な手続きを整理する
- 健康保険や高額療養費制度などの公的支援を確認する。
- 預貯金や保険の書類を整理し、どこに何があるか家族で共有する。
- 遺言書の有無を確認し、必要なら公証役場で作成を検討する。
3. もしもの時に備えて話し合っておく
- 葬儀やお墓の希望を聞いておく(できればエンディングノートに記録)。
- 遺品整理の方針を家族で話し合い、残したいもの・処分するものの基準を決めておく。
- 早めに信頼できる遺品整理業者を調べておき、必要な場合にすぐ依頼できるようにする。
事前に準備をしておくことで、万が一のときにも冷静に対応しやすくなります。つらい話題かもしれませんが、家族みんなが安心できるように、できることから始めていきましょう。
遺品整理で後悔しないためにできる準備
胃がんの闘病を支えるなかで、心のどこかで「もしもの時」を意識する瞬間があるかもしれません。特に病状が進んでくると、看病の傍らで「その後に向けた整理」についても考える必要が出てきます。悲しみの中で急いで判断を迫られるのは、家族にとって非常につらいことです。だからこそ、前もってできることを少しずつ準備しておくことが、後悔の少ない別れにつながります。
以下に、遺品整理で慌てないために今からできる準備を3つの視点でご紹介します。
本人と話し合っておくこと
病気についての話は避けたくなるものですが、少しでも体調が安定しているうちに、話せることは話しておくのが理想です。
- 形見として残してほしいもの、大切にしている持ち物を聞いておく
- 財産や契約関係について、どこに何があるかだけでも共有しておく
- エンディングノートの作成や、簡単なメモでも残してもらうようお願いする
これらの準備があるだけで、残された家族の混乱や心労を大きく減らすことができます。
家族の間で整理の方針を決めておく
いざというとき、家族の間で意見が分かれてしまうと作業が前に進まなくなります。事前に次のようなことを話し合っておきましょう。
- 「何を残すか」「どのタイミングで整理するか」の基準を共有する
- 遺品の中でリユースできるもの、処分するものの判断基準を決めておく
- 必要であれば、誰が中心となって整理を進めるかを確認しておく
「物を処分すること=故人を忘れること」ではありません。思い出や気持ちを大切にしながら、形あるものを整理していくプロセスは、心の整理にもつながります。
専門業者の活用を視野に入れる
もし遺品の量が多い、または気持ちの整理がつかず手がつけられないという場合には、無理をせず専門の遺品整理業者に相談することも選択肢です。
- 見積もり時に費用や作業内容をしっかり確認する
- 遺品整理士など資格を持ったスタッフが在籍しているかチェックする
- 供養や清掃など、遺品整理以外のサービスが必要かも考えてみる
業者を活用することは決して「人任せ」ではありません。家族が自分たちの気持ちに余裕を持ち、穏やかに見送るための手段のひとつです。
どれも難しい話ではありますが、「考えておいてよかった」と思える日がきっと来ます。すぐに行動に移さなくても、「いずれは必要になること」として少しずつ向き合っていくことで、心にも準備ができていきます。
遺品整理の流れと進める際のポイント
いざ遺品整理を始めるとなると、何から手をつければよいのか分からず戸惑うことが多いものです。特に、突然の別れで気持ちの整理がつかないまま進めることになると、作業が思うように進まなかったり、後から「もっとこうしておけばよかった」と後悔したりすることもあります。
ここでは、遺品整理の基本的な流れと、進める際のポイントをお伝えします。
遺品を仕分けする
まずは、残すもの・処分するもの・譲るものを大まかに仕分ける作業から始めます。
- 残すもの:形見として持っておきたいもの、大切な思い出が詰まったもの
- 処分するもの:衣類や日用品など、残しておく必要がないもの
- 譲るもの:親族や友人に形見分けするもの、リサイクルできるもの
「今は決められない」と感じるものは、一度「保留」の箱を作り、後日改めて判断すると良いでしょう。
重要な書類や貴重品を確認する
遺品の中には、後々必要になる書類や財産に関わるものが含まれていることがあります。特に以下のものは、整理の際に慎重に取り扱うようにしましょう。
- 通帳、キャッシュカード、証券
- 不動産関連の書類(権利証・登記簿謄本など)
- 保険証書、年金関連の書類
- 契約書類(ローン、サブスクリプション、クレジットカードなど)
手続きをスムーズに進めるためにも、これらの書類は優先的に探して整理すると安心です。
家財道具の処分を進める
衣類や家具、家電などの処分は、自治体のルールに従う必要があります。自治体によっては粗大ゴミの回収に時間がかかる場合もあるため、早めに確認しておきましょう。
また、状態の良いものはリサイクルショップや寄付団体を利用することで、必要としている人に役立ててもらうこともできます。
部屋の片付けと清掃を行う
遺品整理が終わった後は、部屋の掃除を行い、必要に応じてハウスクリーニングの利用を検討します。特に、持ち家の場合は売却や賃貸に出すことを視野に入れ、原状回復の必要があるかも確認しておくと良いでしょう。
遺品整理業者を利用する場合の注意点
遺品の量が多い、遠方に住んでいて整理が難しい、精神的な負担が大きい場合などは、専門の遺品整理業者に依頼するのも一つの方法です。業者を選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。
- 見積もりを事前に確認し、不明瞭な追加料金がないか
- 遺品整理士などの資格を持つスタッフが在籍しているか
- 供養や買取サービスなど、希望するサポートが受けられるか
信頼できる業者を選ぶことで、負担を軽減しながら遺品整理を進めることができます。
遺品整理は、思い出と向き合う時間でもあります。焦らず、無理のないペースで進めることが大切です。
まとめ:今できる準備と向き合い方
遺品整理のことを考えるのは、決して楽なことではありません。特に、目の前にいる大切な人が闘病中であればなおさらです。「縁起でもない」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、いざというときに慌てずに対応できるかどうかは、今この瞬間の小さな備えにかかっています。
準備とは、何もすべてを決めることではありません。頭の片隅に置いておくだけでも、気持ちに余裕が生まれます。以下のようなことから始めてみましょう。
- 少しだけでも、本人の希望や考えを聞いておく
- 重要書類や貴重品の場所を家族で共有しておく
- 自分が「整理する立場」になるとしたら、誰に相談したいかを考えてみる
- 地域の遺品整理業者や終活サポートの情報を調べておく
「まだ元気だから」「その時になったら考える」と思っていても、時間は待ってくれません。事前の備えは、残される人にとっての思いやりであり、悲しみの中での支えになります。
向き合うことに勇気がいるテーマだからこそ、一歩踏み出す人の背中を押すような情報が、きっと役に立つはずです。今できることを、少しずつで構いません。無理なく始めていきましょう。
参考文献(引用・出典)
- 国立がん研究センター「がん情報サービス 胃がん」
https://ganjoho.jp/public/cancer/stomach/about.html - ONO ONCOLOGY「胃がんの種類」
https://p.ono-oncology.jp/cancers/gc/01/04_type/01.html - 厚生労働省「令和4年人口動態統計」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/index.html - 東京医科大学病院 がんセンター 胃がんページ
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/cancer/stomach/knowledge.html - 消化器がん専門情報サイト「胃がんナビ」
https://gicancer.jp/type/stomach-cancer/ - 国立がんセンター「がんの種類別統計」
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html - 日本胃癌学会「胃癌取扱い規約」要約
https://www.jgca.jp