虚血性心疾患のリスク対策|突然死に備える遺品整理の知識
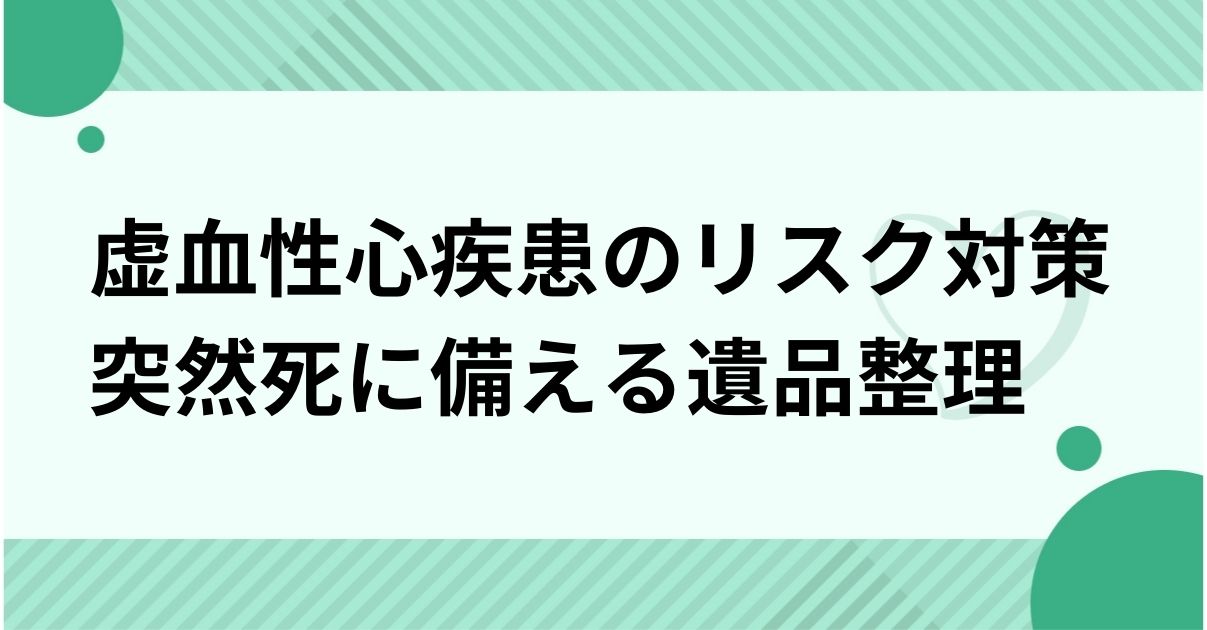
「虚血性心疾患」と聞いて、すぐにピンとくる方は多くないかもしれません。
でも、「元気だったのに、急に倒れて…」 こんな話を耳にしたことはありませんか?
実はその背景にある病気のひとつが、この虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん)です。
- 心臓に血液がうまく届かなくなることで起こる病気
- 「狭心症」や「心筋梗塞」が代表例
- 重症化すると突然死に至ることも
この病気は、ある日突然発症し、そのまま命を落とすケースも少なくありません。前兆がわかりにくいため、普段の生活のなかで備えておくことがとても重要です。
中でも、見落とされがちなのが「もしもの後」のこと。
たとえば、遺品整理や財産の手続きの実務は、残されたご家族に大きな負担をかけることになります。
本記事では、
- 虚血性心疾患の基本知識
- 突然死のリスクへの備え
- 家族が後悔しないための遺品整理の方法
について、フォーマルかつわかりやすくお届けしていきます。
「まだ先の話」ではなく、“今できること”として、ぜひ参考にしてください。
虚血性心疾患の特徴と進行のしかた
虚血性心疾患とは、心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を届けるための血流が不足することで起こる病気の総称です。もっとも代表的なのが「狭心症」と「心筋梗塞」で、いずれも心臓の動脈に異常が起きることで発症します。
この病気のやっかいな点は、軽い違和感から始まることもあれば、まったく前ぶれなく突然命に関わる症状が現れることもある、という進行の読みにくさです。
よく見られる症状と特徴

- 胸の圧迫感や締めつけられるような痛み
- 階段を上ったときや運動時に息切れが起きやすい
- あご・肩・背中に痛みが広がることもある
これらの症状は、狭心症の段階では数分でおさまることがあります。しかし放置すれば、ある日突然、血管が完全に詰まり「心筋梗塞」を引き起こす危険性があります。
また、心筋梗塞になると心臓の一部が壊死し、心臓のポンプ機能が著しく低下します。最悪の場合、数分以内に心停止となるケースもあるため、早期発見と対策が何よりも大切です。
虚血性心疾患の種類と予後に関する基礎知識
虚血性心疾患にはいくつかのタイプがあり、それぞれ症状の現れ方や重症度が異なります。ここでは代表的な3つのタイプと、その予後に関する基本的な知識を紹介します。
主な種類と特徴
- 安定狭心症
運動やストレスなど、心臓に負荷がかかる場面で胸の痛みが出るタイプです。安静にすると数分以内におさまるのが特徴で、薬物療法などで症状をコントロールできます。 - 不安定狭心症
少しの動作や安静時にも胸痛が起こるタイプです。発作の頻度や強さが増していくことが多く、心筋梗塞の前兆とされるため、早急な受診と治療が必要になります。 - 心筋梗塞
冠動脈が完全に詰まり、心筋の一部が壊死する状態です。激しい胸痛や冷や汗、意識障害などを伴い、命に関わる緊急状態です。発症後すぐに適切な処置を受けなければ、突然死につながる可能性もあります。
統計データから見る傾向
- 日本における死亡原因の第2位が「心疾患」
- 心筋梗塞の発症後、1カ月以内の死亡率はおよそ10%
- 発症リスクが高くなるのはおおむね40代以降。特に男性は50〜60代、女性は閉経後にリスクが上がります
こうしたデータからもわかるように、虚血性心疾患は決して珍しい病気ではなく、多くの方にとって現実的なリスクと言えます。
虚血性心疾患の末期症状と家族が知っておきたいこと
虚血性心疾患は、進行すると心臓の機能が著しく低下し、命の危機を迎えることがあります。とくに心筋梗塞を繰り返したり、治療が間に合わなかった場合は、いわゆる「終末期」に入ることもあります。
この段階で起こる身体の変化や、家族が備えておくべきことについて見ていきましょう。
終末期に見られる主な症状
- 息苦しさが強くなる(安静時にも呼吸が苦しくなる)
- 血圧が低下し、意識がもうろうとする
- 手足が冷たくなったり、顔色が青白く(チアノーゼ)なる
- 食事がとれなくなる
- 会話が難しくなる、眠っている時間が長くなる
症状のあらわれ方には個人差がありますが、「呼吸が浅く速くなる」「うとうとと眠っている時間が増える」といった変化は、終末期のサインとされます。
家族として知っておきたいこと

終末期には、本人の意思がはっきり確認できなくなることもあります。だからこそ、早めの段階で以下のような話し合いや準備をしておくことが重要です。
- 医療方針の確認(延命治療を希望するかどうか)
- 緊急時の搬送先や主治医の連絡先の整理
- 在宅医療やホスピスなど、看取りの場所についての希望確認
- 家族の心の準備とサポート体制づくり
突然死のリスクが高い病気だからこそ、余裕があるうちに「もしも」の時のことを話し合っておくと、いざというときに慌てずに行動できます。
家族が直面する負担と早めに考えたいこと
虚血性心疾患は、突然の発症や急変が多いため、家族は心の準備ができないまま「その時」を迎えることがあります。残されたご家族が直面するのは、精神的なショックだけではありません。実際には、さまざまな現実的な負担も一気にのしかかってきます。
ここでは、よくある家族の負担と、できるだけスムーズに対応するための備えについて整理します。
家族にのしかかる主な負担
- 精神的な負担
突然の別れに対する悲しみや後悔、不安感など。とくに「もっと早く気づいていれば…」という思いを抱えやすいのが特徴です。 - 経済的な負担
葬儀費用、医療費の清算、相続税の申告など、予想以上に出費がかさむことがあります。 - 実務的な負担
遺品整理、各種契約の解約、行政手続きなど、時間も手間もかかる作業が次々に発生します。
早めに話し合っておくとよいこと
- 保険の加入状況や預貯金の保管場所の共有
- 本人が希望する治療方針や看取りの場所についての意思確認
- 万が一のときに連絡すべき親族や関係者のリストづくり
- 遺品整理や相続に関する役割分担の相談
こうした備えは、「縁起でもない」と後回しにされがちです。しかし、いざという時に慌てず、そして後悔しないためにも、「元気なうちに話しておくこと」が何よりの家族思いではないでしょうか。
虚血性心疾患の終末期に備えてできること

虚血性心疾患は、急変や突然死のリスクがある一方で、治療を続けながら穏やかな終末期を迎えるケースもあります。いざという時に慌てないために、本人と家族でできる準備について考えておきましょう。
医療や介護の選択肢を知っておく
終末期に差しかかると、治療の目的が「延命」から「苦痛の緩和」に変わることがあります。本人の希望や家族の状況に応じて、以下のような選択肢を検討しておくと安心です。
- 在宅医療(訪問診療・訪問看護)
自宅で医療を受けながら過ごす方法。住み慣れた場所で、家族に囲まれて最期を迎えたい方に向いています。 - ホスピスや緩和ケア病棟
痛みや苦しみを和らげることを最優先にした医療が提供されます。医療者と相談しながら、心身の安らぎを保つ支援が受けられます。 - DNAR(心肺蘇生を行わない意思表示)
延命措置を望まない場合は、事前に「DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)」を表明する選択肢もあります。本人の意思が明確なうちに確認しておくことが大切です。
重要書類と意思の整理
万が一の際に家族が困らないように、必要な情報や書類をひとまとめにしておきましょう。
- 預貯金や保険など、財産に関する情報の整理
- 加入中のサービスや契約の一覧(年金、公共料金、携帯など)
- 通帳、印鑑、保険証券などの保管場所の共有
- 自分の思いや希望を記す「エンディングノート」の作成
- 必要に応じて、公正証書による遺言書の準備
これらの準備を「まだ早い」と感じる方も多いですが、実際に困るのは“突然その時が来たとき”です。少しずつでも始めておくことで、本人にも家族にも大きな安心感が生まれます。
遺品整理で後悔しないためにできる準備
虚血性心疾患は、前ぶれなく突然命を奪うことがある病気です。そのため、「遺品整理」も、いつか必要になるかもしれない未来の話ではなく、事前に少しずつ備えておくべき現実的なテーマといえます。
ここでは、後悔のない遺品整理につなげるために、元気なうちからできる準備について紹介します。
生前整理で家族の負担を軽くする
遺品整理は、ご家族にとって大きな時間的・精神的負担になります。生前にある程度の整理をしておくことで、その負担は大きく軽減できます。
- 普段使っていない物を処分する(衣類、家具、書類など)
- 写真や手紙、思い出の品などを分類し、大切なものを選んで残す
- 必要な書類(保険証券、年金手帳、契約書類など)を一箇所にまとめておく
こうした整理は、「今をどう生きたいか」を見直すきっかけにもなります。
デジタル遺品の整理も忘れずに
スマートフォンやパソコンの中にも、多くの個人情報や思い出が詰まっています。デジタル機器のロック解除ができないと、写真や大切な情報が確認できなくなるケースもあります。
- スマホやパソコンのパスワードを信頼できる家族に伝えておく
- SNSアカウントやクラウドサービスの整理
- 定期的にデータのバックアップを取っておく
「物」だけでなく「デジタルの中身」も、今や大切な遺品のひとつです。
形見分けはトラブルのもとにもなりうる
故人の思い出の品を家族で分ける「形見分け」も、事前に希望を伝えておくことで、あとあと家族間のトラブルを防ぐことができます。
- 大切にしている品物や、託したい相手がいれば、メモに残す
- 高価なものや骨董品は、価値のわかる人に相談しておくのも安心
- 家族で「何をどう残したいか」を話し合う機会をつくる
残された人たちが迷わず、気持ちよく整理を進められるよう、元気なうちから少しずつ準備を始めておきましょう。
遺品整理の流れと進める際のポイント
遺品整理は、亡くなった方の思い出に向き合う大切な時間である一方で、手続きや物量の面で大きな負担にもなります。突然の出来事で慌てて進めるよりも、あらかじめ流れや注意点を知っておくことで、スムーズに取りかかることができます。
ここでは、基本的な進め方と、業者を利用する場合のポイントについてご紹介します。
遺品整理の基本ステップ
まずは遺品の量や種類を確認し、どこから着手するかを決めます。部屋ごと・品目ごとに仕分けると、見通しが立ちやすくなります。
思い出が詰まった品は捨てにくいものですが、「残す」「譲る」「処分する」の基準を家族で共有しながら分けていきましょう。
リサイクルや寄付が可能な物、廃棄が必要な物を整理します。大型家具や家電などは、自治体の回収ルールに注意が必要です。
空き家になる場合や賃貸住宅では、最後に清掃や原状回復を行います。退去日が決まっている場合は、スケジュールに余裕を持って進めましょう。
遺品整理業者を利用する際の注意点
- 信頼できる業者かどうかを見極める
「遺品整理士」などの資格を持っているスタッフがいるか、適切な見積もりや契約書が提示されるかを確認しましょう。 - 料金体系が明確かどうか
「一式〇円」といったざっくりした見積もりではなく、作業内容ごとの内訳を説明してくれる業者がおすすめです。 - 不用品回収との違いに注意
遺品整理は、ただの処分ではなく「気持ちの整理」でもあります。作業の丁寧さや配慮も重視したいポイントです。
大切なのは、「できることは自分たちで」「負担が大きければプロに頼る」というバランス感覚です。無理せず、心と体に余裕をもって進めていきましょう。
今できる準備と向き合い方
虚血性心疾患は、ある日突然、大切な人の命を奪ってしまうことがある病気です。その“もしも”がいつ訪れるかは、誰にもわかりません。だからこそ、「まだ元気だから」「自分には関係ない」と思っていても、少しずつ準備を進めておくことが大切です。
遺品整理や終末期医療の話は、ネガティブに感じられがちです。でも視点を変えれば、それは“人生の整理”を通じて、今をよりよく生きるための前向きな行動でもあります。
- 健康診断を定期的に受ける
- 家族と日常的に気になる体調の変化を共有する
- エンディングノートを少しずつ書き始めてみる
- 保険や契約関係の書類をひとつの場所にまとめる
- デジタル機器のパスワード管理や、連絡先リストを見直す
こうした「今できること」をひとつずつ積み重ねていくことで、将来の不安が少しずつ減っていきます。そして、家族への思いやりや自分の人生に対する向き合い方が、より明確になるはずです。
「準備をすること」は、不安を大きくするためではなく、不安を小さくしていくためのもの。
この機会に、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
参考文献(引用・出典)
- 【令和4年(2022)人口動態統計(確定数)】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/ - 【循環器疾患(心筋梗塞・狭心症など)について】
国立循環器病研究センター(循環器病あれこれ)
https://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/ - 【循環器疾患の予防と管理に関するガイドライン】
日本循環器学会/日本心血管インターベンション治療学会など
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/06/JCS2022_Matsuo.pdf - 【健康づくりのための身体活動基準 2023(生活習慣病予防)】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042110.html - 【介護保険制度について】
厚生労働省(高齢者介護対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html - 【終末期医療に関する意思決定支援ガイドライン】
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000197665.html - 【相続・遺言に関する基礎知識】
法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00044.html